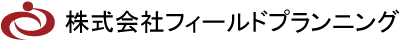-

派遣元責任者講習とは、人材派遣業を営む際に派遣労働者を適切に管理するための責任者に必要とされる講習のことです。
派遣元責任者講習の受講目的や対象者、受講方法をはじめ、オンラインでの受講の特長をまとめました。人材派遣業を営む事業者には、さまざまな要件が設けられています。派遣元責任者の選任もそのうちの1つです。
この記事では、派遣元責任者の概要や派遣元責任者講習の受講目的・対象者・受講方法についてわかりやすく解説しています。オンラインで受講可能な派遣元責任者講習の特長も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。派遣元責任者とは

派遣事業を運営する事業者は、派遣元責任者を必ず選任するよう労働者派遣法で定められています。派遣元事業主は、派遣労働者100人を雇用するごとに1人以上の派遣元責任者を選任した上で、派遣元管理台帳を作成しなければなりません。
はじめに、派遣元責任者の役割や選任する目的、要件を確認しておきましょう。派遣労働者の雇用管理や保護を担う
派遣元責任者は、派遣労働者の雇用管理や保護を担います。主な職務内容は次のとおりです。
- 派遣元管理台帳の作成・記載・保存
- 派遣労働者への就業条件の明示
- 派遣先との連絡・調整
- 派遣労働者の個人情報などの管理
- 教育訓練およびキャリアコンサル
- 派遣労働者への必要な助言・指導
- 派遣労働者からの苦情対応
- 派遣先・派遣労働者双方への派遣停止に関する連絡
このように、派遣労働者が安心して就業できる環境を整備・維持するために、必ず派遣元責任者を選任することになっています。
派遣元責任者を選任する目的
派遣労働者の雇用管理を適正に行い、保護することが派遣元責任者を選任する主な目的です。
従来、派遣事業には「特定労働者派遣事業(届出制)」と「一般労働者派遣事業(許可制)」の2種類がありました。このうち特定労働者派遣事業に関しては、届出を済ませている事業者であれば派遣元責任者を選任することなく労働者を派遣できる仕組みになっていました。その後、2015年に特定派遣が廃止され、派遣事業者は一般労働者派遣事業へと一本化されます。これに伴い、派遣事業者には派遣元責任者の選任をはじめとするさまざまな要件が設けられることとなりました。派遣元責任者の選任も、そのうちの1つです。
派遣元責任者の要件

派遣元責任者として選任できる人物には、次の要件が設けられています。
- 派遣元責任者の業務に専任できること
- 3年以上の労務管理経験があること
- 3年以内に、派遣元責任者講習を受講していること
また、以下の事由に該当する人物に関しては、派遣元責任者に選任できません(欠格事由)。
- 1禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 2健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 3心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 4破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 5第十四条第一項(第一号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 6第十四条第一項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
- 7第十四条第一項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
- 8前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
- 9暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
- 10営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 11法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 12暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 13暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
出典:e-Gov法令検索 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(許可の欠格事由)第六条
資格(受講証明書)の期限
派遣元責任者講習の受講証明書は3年間有効です。したがって、過去に受講した人であっても、3年ごとに再び受講する必要があります。受講日から3年以上が経過した受講証明書は無効となる点に注意が必要です。
派遣元責任者講習とは
派遣元責任者講習の受講目的や対象者、受講方法について解説します。
受講の目的
派遣元責任者講習は、派遣元責任者に対して法の趣旨や派遣元責任者の職務、必要な事務手続きなどを周知するために行われています。講習の主な内容は次のとおりです。
- 労働者派遣法
- 個人情報保護法
- 必要な事務手続き
- 派遣元責任者の職務
- 労働基準法・労働契約法など雇用に関する法令
これらの事項を周知し、適正な雇用管理および事業運営の適正化を図ることが講習の主な趣旨です。
対象者
派遣元責任者講習の受講対象となるのは、下記の条件に該当する方です。
- 派遣元責任者として選任された方
- 派遣元責任者として選任される予定がある方
このほか、労働者派遣事業に関する知識を習得したい方にご受講いただくことも可能です。
受講方法
派遣元責任者講習の受講方法には、大きく分けて対面式とオンラインの2種類があります。
対面式は、講習会場へ出向いて講義形式で受講するタイプの講習です。開催場所や日時があらかじめ決められているため、予定を調整して受講する必要があります。オンライン受講は2021年10月より始まった方式で、パソコンと通信環境があれば受講できます。場所を選ばずどこでも受講できるため、たとえば自宅で受講するといったことも可能です。
フィールドプランニングの派遣元責任者講習(オンライン)の特長

フィールドプランニングは厚生労働省認定機関として、派遣元責任者講習(オンライン)を実施しています。派遣元責任者講習(オンライン)の主な特長は次の5点です。
1. どこでも受講可能
オンライン講習のため、カメラ付きパソコンと通信環境があれば場所を問わず受講できます(※)。全国どこでも、ご自宅からでも受講が可能です。最寄りの対面講習会場を探したり、遠方まで出かけたりする必要はありません。厚生労働省指定カリキュラムに沿った、わかりやすくていねいな解説をご都合のよい場所でお聞きいただけます。
※スマートフォンでの受講はできませんのでご注意ください。2. 開催回数が月10回
フィールドプランニングの派遣元責任者講習(オンライン)は、月10回開催しています。開催日程が豊富に用意されているため、都合のよい日を選んで受講できる点が大きなメリットです。たとえば業務との兼ね合いを考慮して時間を確保しやすい日に受講したり、忙しい時期を避けて日程を調整したりと、柔軟に日程をお選びいただけます。
3. 朝7時から夜23時まで受講可能
フィールドプランニングの派遣元責任者講習(オンライン)は、朝7時から夜23時まで受講していただけます。受講可能時間帯が長く確保されているため、終業後の時間などを有効活用できる点がメリットです。
4. 受講料の支払いは手数料の負担なし
受講料はクレジットカード決済で、手数料はかかりません。オンラインでお申し込みから支払いまでが完結しますので、郵送による申込書や振込用紙のやり取りなども不要です。なお、受講料は一般価格8,400円、会員価格7,400円(いずれも税込)です。
5. 安全でスピーディーな対応
労働者派遣事業の許可・更新手続きに必要な受講証明書は即日発行されます。郵送を待つことなく、すぐにダウンロードできる点が大きなメリットです。
また、派遣元責任者講習としては世界初となるオンラインフェイスシステム(AI顔認証)を採用。ご本人であることを確認した上でご受講いただきますので、セキュリティ面も安心です。フィールドプランニングの派遣元責任者講習(オンライン)の申し込み方法・開催日程
派遣元責任者講習(オンライン)にお申し込みいただく際の流れや、開催日程、講習当日のタイムテーブルをご紹介します。
申し込みの流れ
お申し込みに必要な準備物は「顔写真付きのご本人様確認書類(画像データ)」と、「印刷した受講申込手順書」の2点です。公式サイトにて受講の流れと注意点を確認後、サイト内で受講をお申し込みいただけます。
お申し込み時もしくはお申し込み前に、無料会員登録を済ませておくことをおすすめします。会員登録をすることにより、受講料が1,000円OFFでご受講いただけます。開催日程
派遣元責任者講習(オンライン)の公式サイトでは、月ごとの開催日程が公開されています。ご都合のよい日程を選択して、受講日を確定させましょう。なお、申し込み締め切りは開催予定日の3営業日前(土日含めず)のお昼の11:59までです。
講習タイムテーブル
講習は1回が合計6時間で構成されています。2時間ずつ3回に分けて動画をご視聴いただくと、受講終了後に受講証明書が発行されます。下記は、午前9時に視聴を開始した場合のタイムテーブルの一例です。
8:50
① ID・PWにてサイトに入りログイン顔認証を行う
② 講義視聴用の【再生ボタン】をクリック9:00
Aパート(動画再生2時間)
11:00
昼食60分
12:00
Bパート(動画再生2時間)
14:00
小休憩15分
14:15
Cパート(動画再生2時間)
16:15
受講終了
受講証明書取得(即日発行可)
なお、事務局へのお問い合わせ対応時間は平日9:00〜17:00です。17:00までにご視聴を終えられることをおすすめします。
派遣元責任者講習はフィールドプランニングへ
派遣事業を営む事業者様は、派遣労働者100人ごとに1人以上の派遣元責任者を選任するよう義務付けられています。受講証明書の有効期限は3年間のため、過去に受講したことがある方も3年ごとに受講しなければなりません。
今回紹介した受講の目的や対象者、受講方法を確認した上で、必ず受講しましょう。フィールドプランニングは、厚生労働省認定機関として派遣元責任者講習(オンライン)を実施しています。労働者派遣事業の許可・更新手続きに必要な受講証明書を受講当日にオンラインでデータを取得可能です。派遣元責任者講習の受講を検討している事業者様は、ぜひフィールドプランニングの公式サイトよりお申し込みください。
フィールドプランニング|派遣元責任者講習【オンライン】
公式サイトはこちら